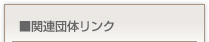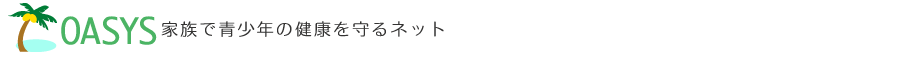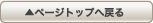子どもに肥満がある場合、その親御さんや兄弟にも肥満がよくみられます。太りやすい、身につきやすいという遺伝的要因を元とし、環境要因・生活習慣が共通の親御さんとお子さんにともに肥満が形成されると考えると、児童のみでなく家族全体での取り組みが不可欠です。
(鶴田悟郎)
学童期、思春期の肥満は将来成人肥満にトラッキング(移行する)ことが明らかです。さらに近年、幼児期の肥満が成人の肥満にトラッキングするという研究報告があります。乳児期の肥満についてはまだ明らかにはされていませんが、近年、妊婦の痩せ志向があり、低出生体重児で生まれた場合、また胎内環境の状態が悪かった児ほど、その後の過栄養にさらされた場合に肥満やメタボリックシンドロームになりやすいという報告もあり、注意が必要と考えられます。
(鶴田悟郎)
いわゆる「ひ弱な肥満児童」が増えています。体脂肪率が高く、除脂肪体重が低い肥満です。見た目の体格はそれほど肥満でなくとも、内臓脂肪型の肥満で体脂肪率が高い肥満のことを「隠れ肥満」といい、肥満児と同様に注意が必要です。
(鶴田悟郎)
診察室の血圧測定は、カフを心臓の高さに保ち、椅子に座って数分の安静を保った状態で測定します。日本高血圧学会高血圧治療ガイドライン作成委員会による高血圧治療ガイドライン2009では、「1-2分の間隔を空けて少なくとも2回測定し、この2回の測定値が大きく異なっている場合には追加測定し、安定した値(< 5mmHg の近似した値)の2回の平均値を用いる」と記載されていますが、様々な理由から、一般に健診や診療の現場ではこのような指針に沿った血圧測定は実施されていないのが現状です。
私たちが学校健診の血圧測定に際して注意している点は、以下の通りです。①測定は静かで適当な室温の環境下で行い、測定前は生徒と会話をかわさないように注意する、②一般に、測定回数は1回とし、血圧高値を示した場合にはさらに数分の安静を保って再度測定して、その値を採用する、③一般に、血圧計は水銀血圧計が用いられているが、精度の高い自動血圧計や電子血圧計の使用も可能である。
(本郷 実)
診察室血圧は、今日なお高血圧診療のスタンダードとされていますが、さまざまな点からその臨床的価値に疑問が投げかけられています。血圧が高めと判定された生徒に対しては、診察室血圧と同等あるいはそれ以上の臨床的価値があると評価される家庭血圧測定や自由行動下血圧測定が望ましいと思います。家庭血圧測定により朝晩1回の測定でも血圧の季節変動や白衣高血圧などの存在が明らかになり、また、家庭血圧と将来の心血管病発症や生命予後との間に関連がみられるなど、十分な臨床的価値が証明されています。特にわが国では家庭血圧計の普及は目覚ましく、家族で家庭血圧を測定する習慣を形成することが出来れば、将来の高血圧発症およびそれに伴う全身の合併症の予防・治療上、大きなメリットが得られると思います。
家庭血圧の測定には、聴診法との較差が5mmHg以内であることが確認された上腕カフ・オシロメトリック装置を用いて、朝は起床後1時間以内、排尿後、座位1-2分の安静後(朝食前)に、晩は就寝前、座位1-2分の安静後に測定することが推奨されています。なお、手首や指用の血圧計は不正確になる場合が多いため、上腕用を用いるのが一般的です。
(本郷 実)
コレステロールは生体の膜成分、ステロイドホルモン、性ホルモン、胆汁酸などの前駆体として重要な脂質です。血液中総コレステロールの1/5は食事由来で、残りは主に肝臓で作られます。LDLコレステロールとは比重が1.006~1.063の低比重リポ蛋白コレステロールであり、HDLコレステロールは比重が1.063~1.210の高比重リポ蛋白コレステロールを指します。LDLコレステロールが高いと虚血性心疾患や脳梗塞の頻度が高くなり、HDLコレステロールが高いとこれらの疾患の発症率が下がります。HDLコレステロールは末梢組織に蓄積した過剰なコレステロールを引き抜き、肝臓に取り込ませると考えられています。
(市川元基)
動脈硬化性疾患予防ガイドライン2007年版では、従来の「高脂血症」から「脂質異常症」に名称が変更されました。これは低HDLコレステロール血症が含まれるのに「高脂血症」とすることに違和感があるからです。したがって、「高LDLコレステロール血症」や「高トリグリセリド血症」をまとめて「高脂血症」という名前で呼ぶことには問題はありません。
(市川元基)
動脈硬化の初期病変であるプラークの内部にはコレステロールが沈着していますが、これはLDLコレステロールに由来するものであることが分かっています。また、LDLコレステロールを下げることにより動脈硬化性疾患が減少することも確認されており、したがって動脈硬化を予防するためには総コレステロールよりもLDLコレステロールに注目することが大事です。
さらに、日本人ではHDLコレステロールが高値であるために総コレステロールが高く、LDLコレステロールは正常な場合がしばしば見られます。本来治療は必要でないこのような人たちを区別するためにも、LDLコレステロールを重視しています。
(市川元基)
通常、HDLコレステロールが100mg/dL以上の場合、高HDLコレステロール血症といいます。HDLコレステロールは動脈硬化防御作用を有するリポ蛋白と考えられ、善玉コレステロールと呼ばれています。従来より、長寿につながるということで「長寿症候群」と呼ばれていました。一方、最近の研究では遺伝的にある種の酵素蛋白(CETP)が欠損する場合にも高HDLコレステロール血症がみられ、その疾患では逆に冠動脈疾患保有率が高いという報告もあります。しかし、まだその疾患の診断や検査方法は確立しておりませんので、現在のところは高LDLコレステロールと低HDLコレステロールによる基準によって判定してよろしいと考えます。
(市川元基)
糖尿病は血糖(血液中のブドウ糖)が高くなった時、血糖を下げるインスリンというホルモンの欠乏あるいは作用の低下により高血糖になる病気です。インスリンは膵臓のβ細胞で産生されます。この膵臓のβ細胞が自己免疫などによって破壊され、インスリン欠乏状態になって血糖が高くなるのが1型糖尿病です。これに対し、インスリン作用の低下のため、血液中のブドウ糖が筋肉、肝臓、脂肪組織などに取り込まれにくくなるのが2型糖尿病です。このため2型糖尿病では血液中のインスリン濃度が高くなります。
(市川元基)
ヘモグロビンA1Cは、採血時から過去1-2ヶ月間の平均血糖値を反映しているため、血糖のコントロールの状態を知る上で血糖値に比べて優れた指標といわれています。ヘモグロビンA1Cは赤血球寿命と関連があるため、出血、鉄欠乏性貧血回復期、溶血性疾患などで低値をとることがあり、解釈する場合には注意が必要です。
(市川元基)
表に代表的な食品のプリン体含有量を示します。動物の内臓や魚の干物などは100gあたりプリン体を200mg以上含み、高プリン食品と呼ばれます。低プリン食を毎日摂ることは困難なため、高プリン食を極力控え1日の摂取量が400mgを超えないようにするのが一般的です。
食品のプリン体含有量(100gあたり)(高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン第2版より)
| 極めて多い (300mg〜) |
鶏レバー、マイワシ干物、イサキ白子、あんこう肝酒蒸し |
|---|---|
| 多い (200〜300mg) |
豚レバー、牛レバー、カツオ、マイワシ、大正エビ、 マアジ干物、サンマ干物 |
| 少ない (50〜100mg) |
ウナギ、ワカサギ、豚ロース・バラ、牛肩ロース、牛タン、 ベーコン、ツミレ、ほうれんそう、 |
| 極めて少ない (〜50mg) |
コンビーフ、魚肉ソーセージ、かまぼこ、焼ちくわ、さつま揚げ、 カズノコ、スジコ、豆腐、牛乳、チーズ、バター、鶏卵、 とうもろこし、ジャガイモ、サツマイモ、米飯、パン、うどん、 そば、果物、キャベツ、トマト、ニンジン、大根、白菜、海草類 |
(本郷 実)
まず行うのは血液検査です。一回の採血で、少量の血液から様々な情報が得られます。次に、腹部超音波検査(エコー)です。肝臓の形、肝臓の中に何かできていないか、肝臓に脂肪がたまっていないか、他の臓器に異常がないか、を調べます。放射線を使わず全く痛くないので、安全で極めて有用な検査です。どちらも近くの医院やクリニックで簡単に行うことができます。
(田中直樹)
残念ながら確実な予防法はありません。ただし、バランスのよい塩分控えめな食事、ストレスの少ない生活、妊娠中の適正な体重増加は予防に役立つ可能性があります。妊娠中は当然ですが、妊娠前からこのような生活への配慮が重要です。
(金井 誠)

「青少年のメタボリック
シンドロームを考える」
研究会
〒390-8621
長野県松本市旭3-1-1
信州大学医学部保健学科
伊澤研究室内
TEL:0263-37-3506